令和六年一月中旬 埼玉県秩父市の恒持神社に参拝しました。
ここの本当のお目当ては境内社の諏訪神社。恒持神社の御本殿覆屋とは別棟になっています。

明治十三年(1880)建立
明治四十一年(1908)恒持神社末社として合祀
工匠 荒木和泉(藤原脩安)
彫師 熊谷玉井村住 小林栄次郎 (秩父市公式サイトより転載)
噂に違わぬ 見事な御本殿が鎮座していました。

兎ノ毛通しには鳳凰。中備は子引き龍。木鼻は獅子と獏です。

懸魚の影に隠れて 唐破風下にも龍がいました。

向拝中備の龍。

扉も凄い事になっています。

向拝柱は 珍しい事に左右とも昇り龍。刺青では「昇りっ放しで良くない」と言って嫌う人が多いです。


この覆屋は 元々は周りにぐるりと開口部があった様ですが 今は塞いであります。なので節穴や板の隙間から失礼しました。

向拝柱を横から見ると こんな感じ。

胴羽目は 三国志演義中盤の名場面の一つ「長坂坡の戦い」から 張飛大鬧長坂橋。長坂橋で大喝する張飛翼徳です。
お得意の合成でどうぞ。

長坂橋に立った張飛は 迫り来る曹操軍に向かって「燕人張飛 これにあり! 俺と命がけの勝負をしたい奴はいるか!」と大喝します。何千人(文献によって数十万人)もいる曹操軍が張飛のこの一喝でビビります。

脇障子は斜めについていて おそらく曹操軍兵士だと思いますが 張飛から逃げているのか 独立した絵柄なのかは 分かりません。どちらにしても ちょっと楽しそうな感じです。

腰羽目には唐子の獅子舞がありました。

残念ながら背面は 隙間がうまい具合に並んでいなかったので 胴羽目全体は見えませんでした。
が 明らかにこれも三国志演義の名場面「長坂坡の戦い」から 趙雲救幼主でしょう。劉備の妃・糜夫人に幼主・阿斗を託された趙雲は曹操軍の中を単騎脱出します。

さて いよいよメインの左面。こちら側には節穴が沢山あります。

ただ 非常に暗いのが難です。

胴羽目は三国志演義序盤の名場面 三顧茅廬。いわゆる三顧の礼です。

劉備玄徳が諸葛孔明を軍師に迎えようと家を三回訪ねて三回目でやっと在宅していたが 孔明はお昼寝中だったという場面。劉備は目が覚めるまで待ったと言います。

童子「先生はお昼寝中だよ」
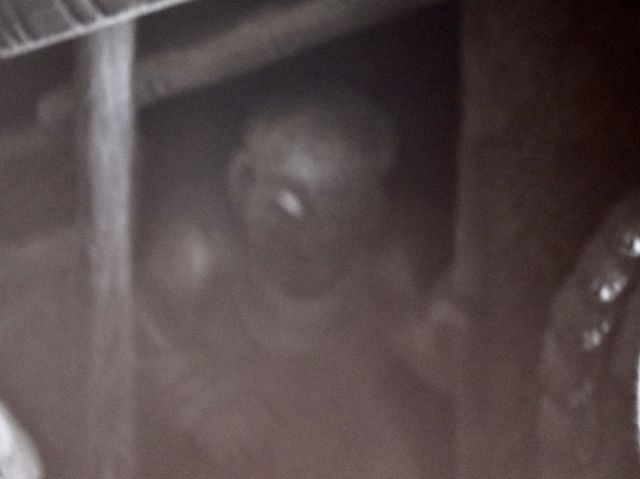
劉備「それではお目覚めになるまで 待ちましょう」

張飛「へ⁉︎ 何言ってんですかぃ兄貴! 奴ぁ寝てんですぜ 帰りやしょう!」

関羽「静かにせんか!さもないと貴様の髭に火を着けるぞ!」


脇障子は青龍偃月刀を持った 関羽雲長。こちらは胴羽目とは別の構図なので 右側脇障子も独立した絵柄なのか それともこちらの関羽とセットなのかも知れません。

腰羽目は司馬温公瓶割。水を張った水瓶に落ちた友人を助ける為に躊躇なく高価な瓶を割ったという司馬光の話ですね。

木階下には童子の力神がいました。今さっき気がついたので 鮮明な写真はありません。

海老虹梁の龍。



間近で鑑賞したい御本殿でした。
刺青師・龍元
030-02(2024.03.26)



コメント
ここは小さいですが凄いですね!!こちらの例祭日を聞いていたのですが、メモが無くなってしまい、ガァ~ん。確か8月の前半だったような?
秩父はR299経由ですが道路に縦溝が掘られていて(グルービング工法)これはバイクがパンクした時の感覚とそっくりなので、トラウマになります。そう言う理由から秩父は避けています(笑)
おはよう御座います 錺さん、
以前「8月第一日曜日、または、10日前後の9時からと聞いたが、結局どちらか分からない」と言ってましたね。
バイクのパンクはいやですね。昔、原チャリ通勤をしてた時に、パンクして泣きながらバイクを引いて帰った事が何度もあります。299号は単調でつまらないので、私は一本下の県道飯能下名栗線を使う事が多いですね。細い道が好きです。